砂丘の夕べ
執筆:荻白(ハミルコ)
挿絵:雨月星一(ライル・カマル)/St(ルナ)
クローブを飯盒に詰め込んで炊き上げた、夕暮れ独特の湿気った甘い風が吹いた。挿絵:雨月星一(ライル・カマル)/St(ルナ)
このあたりでは風が強く、砂丘の位置さえもよく変わってしまうのに、今日は眼や耳を心配しなくてもいい、悪くない日だった。
それでも、この夕暮れの空気は、早く屋根のある寝床に帰れとせかすように心を煽るのだ。
「まずはじめに…」
向こうの砂丘に、熟れ過ぎた真っ赤な杏が叩きつけられるように沈んでいく。
沈み切る前に杏をついばもうと、赤黒い眩しさに向かって影絵の鳥が飛んでいく。
いやにやる気の無い赤黒い夕焼けは、星のない夜の前触れと不安になったルナは後ろを振り返り、東の目安星が辛うじて健在であることを確かめた。
ライルは請うて、もうずっと東のほうを向いていた。西日が眩しいのである。
つまり誰も自分のほうを向いて話を聞いていないのに、瞼のように真っ赤な太陽を背負ってハミルコは続けた。

「歓迎の意を。並びに、感謝の意を。
今日君たちとこうしてお茶を飲めるのはこの上ない悦びさ。
…まあね、長ったらしい前置きはさておくことにするよ。だから僕は長ったらしい前置きをさておいて話の先を急がなきゃいけない。君たちが飽きて帰ってしまうと何もかも失敗だ。
今日も日は暮れる。昨日も暮れたようにね。明日は、まあ暮れるか分からないのが心苦しいところだが、今日はここまで太陽が膝までお布団に足を突っ込んじゃったんだから慣性的に言ってほぼ間違いなく暮れる。
さてさて、話をするに当たってまず前提としてこの一帯に伝わる伝説を!」
座椅子の上に立ち上がった男は、大げさにばさばさとマントから冊子を取り出した。
捲りやすく描きやすい、とどのつまりスケッチブックだ。
表紙をめくれば、児童文学風の大きな文字で

『とわみずの壺』
「それは何ですか?」
ルナは温くなったチャイグラスを傾けた。
温くなったのは、彼が短くするはずだった前置きの結果だったので、話をスムーズに進めたいのだ。
「興味を持って貰えて嬉しいよ!君も壺の素晴らしさを知っているんだね」
「いえ」
「そうか、まだ興味の持ち始めだったよね、今日は壺の素晴らしさを伝えるために集まって貰ったんだった」
「そうじゃなかったはずだから、話を進めねえか」
「そうそう」
『昔、この地方一帯は砂漠も砂漠のド砂漠でしたが、
暮らす人々は一切水に困ることはありませんでした』
「そりゃまた、不思議だな」
「だろぅ」
『その秘密は町の真ん中にあった、一つの壺。
柄杓でいくら汲んでもあとからあとから水が溢れ出し、
喉は乾かず、畑は乾かず、街中に水路が張り巡らされ、ハンマームは住民全てを泳がせて余りあり』
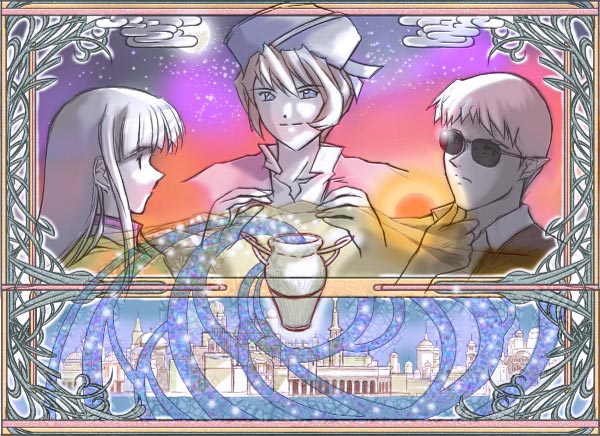
「魔道具…にしては…」
ルナは小首をかしげた。
「無理のある性能だな」
ライルも応える。そんな大層な効能の魔道具など、聞いたことがない。
「そりゃきっとすごい魔道具なのさ。
世の中に一個ぐらいそういうものがあったっておかしくない」
「ま、お伽話だかんな
…でもそんなものがあったらまるっきり世界観が変わっちまうな」
『しかしいつしか壺は失われ
町は元通り うらぶれて山河なし』
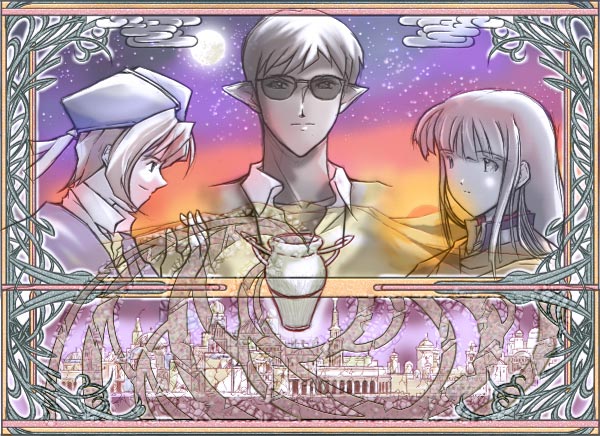
「…たしかに、今現在そういうものがある町には見えないですよね」
さびれた町の現状を思い出してルナは頷いた。
「歯切れの悪い話だな、いきなり無くなったみたいで」
「たしかにそこは気になるところだね。
だから僕も調べてみたのさ」
最後の力を振り絞って砂漠を赤く染めようとしていた日は、全く沈んだ。
誰となしにランプに普段の習慣通りに火を灯す。
空に灯りを灯す人は、今日はおやすみのようだった。円座になった三人の影だけが赤く浮かび上がる。
「するとね、こういう噂話が耳に入ったのさ。
壺は経緯あって隠されているっていうんだ。
壺はあの、町からちょうど良く見える、大砂丘の裏。
丁度女の上唇が地面から突き出しているみたいに形よくなっている砂山があって、その中に、誰も取り出せないように閉じ込められたんだと」
「『閉じ込められた』ですか」
「うん?言葉のあやかな?まるで動物みたいな言い方だよね…『自分が』閉じ込められたかのような言い草だし…」
「砂山のことは知らないが、経緯ってのは」
「僕もよく分からなかった、これは『どこからともなく聞いた話』なんだよ。
なんで、実際探しにいってみようと思ったんだよね。
さて、ここからが今回の本題さ」
ランプの炎が湿気った風に揺らされると、顔の輪郭も歪むようで妙な感覚になる。
頬を押さえ、ルナは思い出していた。どうしてこのような話を隊商宿から離れて砂漠の真ん中でしているのか。
たまたま、隊商が大忙しで誰もが出払い、ルナとライルだけがそれぞれの夕刻を過ごしていたところに、この男が現れたのだ。
「折り入って頼みがあるんだ。お茶をしないかい」
そういう彼はとても機嫌良さそうに、でもどこか焦った顔だとルナには見えた。
しかし今の彼には、焦りなど微塵もなく、ゆっくり更ける夜を楽しんでいるかのようにも見える。
まるで既に目的を果たしている、かのような。
「それで一人乗りの駱駝を出したのさ」
「一人で?」
「手柄が独り占めがいいんだよ。水を売る商売でも新しく始めようかと思ってね。
っていうか、誰か誘ってやってもよかったんだけど、たまたま誰もいなかったんだよ…皆して忙しいことがあるもんだね。
それにしても誰か一人ぐらいいてもいいのになぁ…と思ったけれど。
…脱線したね。
で、それは丁度今日みたいな夕方だった。砂漠のただ中なのに湿気った風で、甘いような臭いがたちこめていて。
駱駝を進めるうちにすっかり真っ暗になって…。
砂漠を行くと…あそこで何か影が動いたか?トカゲかな?サソリかな?…何もいない。
頬撫でる風は既に砂になって、いま蹄が踏みしめている過去の人々の恨みの吐息かもしれない。…そんなはずはない。
このあたりの砂なんて、風が吹けば様変わりするはずなのに、そこに子供の足跡がある…まさか。たまたまそんな風にへこんでいるんだ。
カリカリ、カリカリ、とよく分からない音がする…何か、カジっているのかな。たぶんきっと…ネズミとかがね。
誰もいない
砂漠を行くうちに、ぽっこりと砂が盛り上がっている場所があった。
…そこにさしかかると、後ろに乗った案内の女が「ここですここです、私怖いです」なんて騒ぎ出してね、僕の首におもいっきりしがみつくからもう首が折れるかと思ったよ、実際グキって音がしてあれはもーやばかった」
ライルは首を傾げた。妙な話だ。
ルナを見やると目が合う。彼女は訝しげに頷いた。
「…それで?」
「結局…まあ、こうしてほうほうのていで帰ってきたのさ
壺は結局見つからなかったよ」
ランプの炎が風に煽られ、ぶわっと大きく膨らんで消えた。
何か絶対に消えてはいけないものが消えたような気がして、二人の心にもそれぞれ夜が忍びこんでくる温度が感じられた。
「僕の話を聞いたね?」
月のない暗闇に、半ば笑ったような声が聞こえた。
クローブを飯盒に詰め込んで炊き上げた、夕暮れ独特の湿気った甘い風が吹いた。
向こうの砂丘に、熟れ過ぎた真っ赤な杏が叩きつけられるように沈んでいく。
沈み切る前に杏をついばもうと、赤黒い眩しさに向かって影絵の鳥が飛んでいく。
ルナは、グラスの中に残ったチャイで喉を温め、立ち上がった。
そろそろ隊商宿に帰らないと日が暮れてしまう。
ライルも空になったグラスをハミルコに返すところだった。
帰り道が暗くなる場合に備えて持ってきたランプは、持ち上げてみると存外軽くて、確認してみると案の定中は空だった。多分どこかでこぼしてしまったのだろう。
「いい暇つぶしになりました。ありがとうございます」
「今日は特別誰もいなくて退屈だったし…砂の上でお茶会なんて酔狂も悪くねえな
特に肝心の怖い話があんまり怖くないところがよかった」
「ふっふ、それじゃ今度の機会には君たちがもうちょっと怖い話をしてね」
立ち上がって伸びをすると、しばらく座り込んでいたせいで背骨がぽきぽきと鳴った。
「退屈な夕方にはちょうどいい催しかもしれないですね。
ここの当たりは夕方には凪ぐようですし、夕日を見ながら談話も乙なものです」
「そろそろもうちょっと人数が帰ってきているはずさ。
次回はもっと賑やかに開催できるだろうね」
茶道具を畳んで、隊商宿に急ぐ足並みの中で、ルナとライルはそれぞれ考えていた。
次に誰かを誘って砂の上の茶会で振舞う「お話」の内容を。
それはきっと楽しい茶会になる。そう思うと足の運びもどんどん早くなっていくのだった。
別にそこまで茶会や会合の好きな気質ではない。それでも、あの場所で茶会をやるのは悪くない考えだと思える。
たとえば。
人食い壺…美しいが二回と見ることが叶わないから、そう、言わば「永遠見ずの壺」が、自らありもしない伝説をでっちあげて噂を作り出し、旅人を呼び出して魂などを食らってしまう。
旅人は魂がないから、昼間にはその手のモノの性質上出歩きづらくて、夕方になると隊商宿に帰ってきて、仲間を砂漠に連れ出す。
そうしてミイラ取りがミイラではないが、ネズミが増えるのと丁度逆のようにどんどん皆人食い壺に食べられてしまうのだ。
そんな作り話をしたらきっと面白いのではないだろうか。