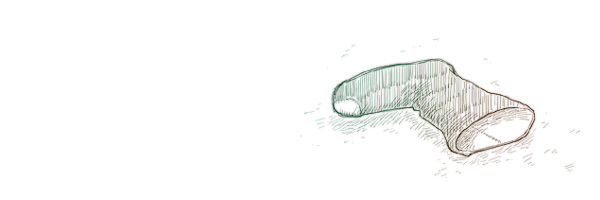オヤジと少女と白いネコ
執筆:春乃はじめ(ヌール・バースィル)
挿絵:時雨(ライハーネフ)/森(ハサダール)
隊商。それは商品、あるいは人そのものの移動中に盗賊団や魔物などの危険から集団的に身を守るために、商人をはじめ、護衛、芸人などさまざまな得意分野を持った様々な人種がひとつの集団を形成して砂漠を闊歩すること。挿絵:時雨(ライハーネフ)/森(ハサダール)
その職業分布は集団によっても異なるのだが、とある集団にて圧倒的に足りていないのが、鳥獣使いと料理人だ。二百に迫ろうという人数の食事とラクダやラバといった動物の世話を、なんとそれぞれ両手で数えるに事足りる精鋭を中心こなしているのだ。
本気か冗談かはわからないが護衛ですらシフト制で当番がまわってくるというのだからもちろん見習いに手伝いの仕事がまわってこないわけがない。
もっともどんな集団であっても、どんな職群であっても、そう――見習いであっても働く見習いと働かない見習いがいたりして――。

日が傾きかけた頃。絨毯で有名な夢織りの町を歩く少女が二人。
ひとりは青色のポニーテールの少女、ヌール・バースィル。働く見習いだ。さんさんと輝く太陽を隠すように両手で加害者とも被害者ともいえるそれを高く持ち上げると、ヌールはそれと目を合わせて問いかけた。
「どうしてこうなったのかなぁー?」
しかしそれは首を傾げるだけで決して答えてはくれなかった。
「ふふ」
もうひとりは桃色のサイドテールの少女、ライハーネフ。働く鳥獣使いだ。日に焼けるのが嫌いで大きなマントをはおっているため、今はよくは見えないが、髪より淡い桃色や橙色といった可愛らしい花を連想させる服を着ている。肩が出て、胸元が出て、太腿が出て、臍が出て……。日に焼けるのが嫌なら露出度の高い服なんて着なければいいのにとも思うのだが、そこは歩く“乙女心”のライハーネフ。“可愛くお洒落したい”と“けれども日焼けしたくない”の葛藤の結果が今の姿なのだろう。そんな彼女は特徴的な黄と青の混じった瞳でヌールとそれの様子を伺い、くすりと笑いながら続けた。
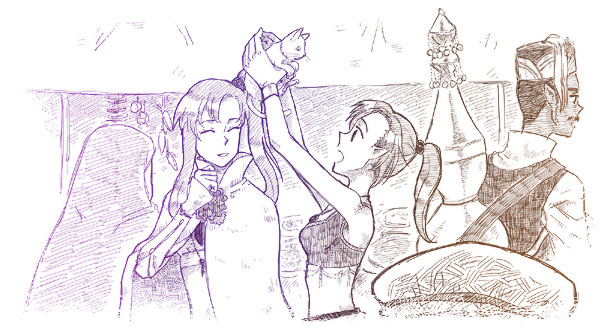
「まぁまぁ。楽しかったからいいのです! あ。あたしにも抱かせてよ」
「ほぃ」
ライハーネフに渡すと慣れた手つきで胸元に抱き寄せる。するととたんにそれは気持ちよさそうな声でひと鳴きし、心地よさそうにライハーネフの体に頬をこすりつけた。
ヌールに対する態度とどこか違う。
この懐き方の差が、人柄によるものなのか、彼女が鳥獣使いだからなのか他の理由があるのかはわからない。それはさておき――
(どうしてこうなったのかなぁー?)
ヌールは先ほどそれ――小さくて白くてふわふわしたネコ――にした質問を心の中で繰り返した。
遡る事数時間前。ある天幕を目指して歩く少女が二人。
青色のポニーテールの少女、ヌール・バースィルとその後ろを追いかける桃色のサイドテールの少女、ライハーネフだ。
「あー! みーつーけーたー」
天幕にずかずかと入り、お目当ての人物を見つけるとヌールは声をあげた。
ヌールが指差した先では男が一人、天幕のクッションに背中からもたれかかっていた。オリーブ色のツインテールのおっさんはハサダール。働かない見習いだ。そのツインテールの癖っ毛は、ハーフアップで片側にお団子を作っていたりお下げだったりと、ポニーテールに拘るヌールとは異なり、日によってころころ変わる。

「こんにちは!」
後から入ってきたライハーネフは元気に笑顔で丁寧なお辞儀と共に挨拶をした。
果たして我らが隊商の乙女代表といっても過言ではないライハーネフはハサダールの身だしなみを見てどう思うだろう。緑地に青ストライプのズボンはいい。問題は上半身だ。薄汚れた服は着ているがすっかり前がはだけおり、胸も腹も露になっている。失礼を承知で言葉を選ばずに言うならば決してキレイな体ではない。ヌールはまったく気にしない。そのあたりはもう少しライハーネフから乙女心の何たるかを学ぶべきなのかもしれないが……。
どちらかといえば気にしてしまうのは右腕だ。あって然るべき肘より先が見当たらない。生まれたそのときからないのか人生を歩む中でなくしたのかはわからないが、それを聞いたところで誤魔化されて終わるのは目に見えていたので敢えて聞いていない。いわゆる“大人の事情”と呼ばれるものだ。ちょうど同時期にもう二人ほど片腕のない男が入隊したものだから“流行か何かかしら”と不謹慎なことも考えたが、やはり大人の事情で真相はわかりそうもないので大人しく“大人って大変”という結論に落ち着くことにした。
「よっ、おめぇらオレになんか用でもあるのか?」
ハサダールは明らかにイラついているヌールを特に気にするわけでもなく軽く左手を上げて軽口を叩いた。もちろん用事がなくてずかずかやってくるものか。
「えぇそうよ。っていうかハサダールさんこそ、ライに用があったはずじゃないのかしら?」
「んー……遊ぶ約束でもしてたっけか?」
「ちっがーう」
「あの! 今日ラクダのお世話のお手伝いをしてくれることになってたと思うんです。でもハサダールさんが来なかったからヌールちゃんが手伝ってくれて……」
更に遡る事数時間前。面白いことを求めて街中を歩く少女が一人。
と始めると長くなるので簡潔にまとめてしまえば、ひとり重そうにラクダの餌を運ぶライハーネフを見かけたヌールが彼女を手伝ったことから始まった。なんでも共に仕事をするはずだった見習いがひとり来なかったというのだ。それが誰かといえば……もはや言わなくてもわかるだろう。自分がサボって自分が痛い目をみるなら構わないが、サボったせいで友達が大変な思いをしたとなれば一言物申さねばなるまい。
「あたしがいなかったらライの腕が壊れちゃったかもしれないのよ?」
「いやぁ、オレの腕なんてもう壊れちまってるからなぁ」
そういって失った右腕を上げてみせる。先がないため、肩を挙げてもシャツの袖半分は力なくぶらりと垂れ下がったままだ。もちろんそれがサボっていい言い訳になるはずがない。
「そんなこといってもダメよ。今度また“動物のお世話”とか頼まれごとをサボったりなんかしたらマリーヘさんにいいつけちゃうんだから」
泣く子も黙る世話人マリーヘ。彼女を敵に回すと隊商生活に少なからず支障をきたすため、脅し文句としては使いやすい。と思っているが目の前のハサダールはニヘラニヘラと笑っている。どうやら効果はいまひとつのようだ。
「んあ? オレだって“動物の世話”ならしてたっつーの。ほれ」
「えー。そんなバレやすい嘘ついたって……」
「にゃ」
「……え」
口がぽかんと開いてしまったヌール。
「……あ!」
頬がすっかり緩んでしまったライハーネフ。

「な? オジさん、ウソつかない」
ハサダールが脇にあるクッションをどかすと、そこから一匹のネコが顔を出した。小さくて白くてふわふわしていて可愛い子ネコ。
固まるヌールを差し置き、先に動いたのはライハーネフであった。可愛いものと動物が大好きな彼女だ。可愛い動物が出てきたのだからじっとしていられるだろうか。
近づいてひょいと持ち上げると、慣れた手つきで胸元に抱き寄せる。するととたんにそれは気持ちよさそうな声でひと鳴きし、心地よさそうにライハーネフの体に頬をこすりつけた。
「ハサダールさん、この子どうしたの?」
「はっはっは。拾った」
「はぁ!?」
ポカンと開いたままの口が更に大きく開く。相変わらず固まったままのヌールをよそにハサダールはライハーネフをみて感心した。
「ほぉ、ピンクの嬢ちゃんにはよく懐くなぁ。オレにはサッパリだったんだけどなぁ」
「ちょ、じゃあ何で拾ってきたの!」
ようやくツッコめる程度には現実に追いつくことができた。このハサダールという男、一体何を考えているのか。……多分何も考えてない。
「いやぁ、落ちてたもんで。それに食えるかもし――」
「ダメです!」
ヌールがツッコむ前に、ハサダールが言い終える前にライハーネフが語気を強めてツッコんだ。常識的に考えれば食べるはずがないのだが、仮に先の発言が本気ならばまだ何も考えていないほうがましだった。
「で、どうするのこの子?」
「どうもしねぇさ。気に入りゃここに居つくだろうし、気に入らなきゃでていくんじゃねーの?」
半ば予想通りの何も考えていない答えにヌールはため息をついた。もっとも“勝手に拾ってきた”という前提さえ目を瞑ればハサダールの答えには概ね賛同だ。食べられさえしなければネコの自由意志に任せておけばいい。
(よし)
突然登場したネコにすっかり惑わされてしまったが、当初の目的であった見習い先輩としての説教もしたし、そもそも説教してもまったく無駄な気がするし、そろそろ戻ろうかと思ったそのときだった。
「あたし達で返そうよ!」

ライハーネフの口からそんな台詞が飛び出した。今度は一体何が始まろうとしているのか。あまりに急展開が続くものだからヌールの頭はまったく追いついていない。そんなヌールのことを察したのか、ライハーネフは続ける。
「見て見て! ほら、このネコ、首輪がついてるの。つまり飼いネコってことよね!」
ライハーネフがネコの首もとの毛を指で分けると、確かにそこには細い首輪があった。
するとハサダールは他人のネコ攫ってきたというのだろうか。いや、ハサダールがそんな面倒くさいことを自らすすんでやるわけがない。おそらく飼い主と逸れてしまった飼い猫をたまたま拾ってしまったといったところだろう。
「でもどうやって探すの?」
実はヌールはかつて香雲の花という町で似た様なシチュエーションに出くわしたことがあった。そのときは今回と逆で、飼い主の依頼をうけたマリーヘの依頼でネコのほうを探した。余談であるが何を隠そうそのとき探さなければならなかったネコが、小さくて白くてふわふわな子ネコで――つまりは今ライハーネフの腕の中にいる子ネコと容姿が瓜二つだったのである。
閑話休題。小さい、白い、ふわふわだけでネコが探せるわけがない。そのときは随分奔走した覚えがある。まして今回はノーヒントだ。ライハーネフに何か策はあるのだろうか?
「えっへん! 市場でお買い物しながら聞き込み調査です!」
そうきたか。朝から今までいろいろなことが起こりすぎて上機嫌とはいいがたかったヌールだったがライハーネフの“買い物がしたい”という正直な意志の篭った提案についつい笑ってしまった。
「はは、何それー! 飼い主探しがメイン? お買い物がメイン?」
「か、飼い主探しだよもちろん! でもせっかくだからこの町のお店もいろいろ見たいなーって。一緒に行ってくれる?」
ライハーネフは笑われると思っていなかったのか、少し頬を赤らめた。親友であるライハーネフの、それも面白そうな頼みごとなら断る理由はどこにもない。
「わかったわ。じゃあさっそくそのネコちゃんの飼い主を探しにいきましょー!」
「お。じゃあついでに酒も買ってきてくれよ」
「自分で買ってきなさい!」
頼みごとをすっぽかした男の頼みは聞いてやるものか。
こうして、ネコの飼い主探し(買い物もするよ)が始まったのである。
「……ちゃん」
「ヌールちゃんどうしたの? ぼーっとしちゃって」
子ネコを抱いたライハーネフに問いかけられ、ヌールは我に返った。
「ほぇ? あ、ごめんごめん。その、どうしてこうなったのかなぁーって振り返っていたのよ」
「えへ、本当にいろいろあって楽しかったね!」
「うん」
それはもういろいろあった。ハサダールと別れる前にもいろいろあったが別れてからも濃厚な時間であったあった。ライハーネフとの買い物は今回が初めてではないが、相変わらず楽しそうに店の品物を眺める。特にアクセサリーや服、この町の特産である絨毯や布のお店の目の輝きようが半端ではない。イヤリングやネックレスをとってはつけ、とってはつけと試着を繰り返すものだから、ついさっきまでヌールがネコを抱くことになっていたのだ。
(これが乙女なのね……!)
この買い物ツアーで自分に足りていないものが何か、少し分かった気がした。
そういえば……。
「ライ、さっき夢折りの絨毯の切れ端買ってなかった?」
「うん? 買ったよ!」
夢折の絨毯は願いことを叶えてくれるという。切れ端でどれほどの効果があるかはわからないが、何か願いがあって買ったに違いない。
「何のお願いするの?」
「え、あ、え、え、そ、それは言えないのデス!」
ヌールの何の気もない質問にライハーネフはヌールの思っていた以上の狼狽を見せた。頬も耳もリンゴのように真っ赤に染まる。
(こ、これも乙女なの……!?)
「え、なになに何なのよ!」
「ひみつデス!」
乙女の核心に迫るべく追求するも照れるばかりで答えてくれない。
「えー!」
結局この日はライハーネフの願いも、ネコの飼い主も分からぬまま、それぞれの帰路につくこととなった。
朝からばたばたしっぱなしの慌しい一日。今日は互いにぐっすりと眠れることだろう。
……がその前に。
日もすっかり落ちた頃。ある天幕を目指して歩く少女が一人。
青いポニーテールの少女、ヌール・バースィルだ。
特に伝える義務もないとも思ったが元凶である以上顛末を知っておいてもらいたいと思い、再びハサダールを訪ねることにした。
「やっほー!」
天幕を覗くと昼間とまったく同じ格好でハサダールがだらけていた。
「おう、どうだったんだ?」
「まぁまぁかしらね。なんかこの町の市場で猫を探してる人がいるみたい。今晩あのネコはライが預かってくれるって。明日もまた探してみる」
「そりゃよかったな」
「にゃ」
「……え」
最近、いや、さっき、まったく同じ体験をしなかっただろうか。
「おう。また拾った」
ヌールは最近、いや、さっきと同じように再び固まった。まったくこの何も考えていない男は一体何を考えているのか。
「……あー! もう自分で返してきなさーい!」
ヌールは感情に任せてそこらに脱ぎ散らかされたクサい靴を拾うと、全力で天幕の外に向かって放り投げた。
「もうこの人しらない!」
ついでにさじも投げた。