アナマリード
執筆:整野(セツィアツィルト)
挿絵:小此木(ナーターン)/yuran(リファー・アスィール)
「というわけで、君に運命探しを依頼するとしよう」挿絵:小此木(ナーターン)/yuran(リファー・アスィール)

少年、というよりは青年と言ったほうがいいんだろうか。暁の空みたいな色の髪を後ろに束ね、褐色の肌を持った目の前の子は、僕が彼をどっちのカテゴリーに入れるべきか悩んでる事も知らずにぽかんと口を開けていた。
「………え?」

街角の茶館でお茶をしていた彼は、僕の言葉に目も丸くして顔いっぱいに疑問符を浮かべている。出来心で束ねられてる髪を引っ張りたいという衝動をぐっと堪えながら、僕は言葉を続けた。
「どういう運命でも構わないけど、できれば劇的な感じのがいいなあ。宿命のライバルとか、ウケがよさそうな歌が出来そうな題材が欲しいんだ」
「ちょ、ちょっ、ちょっと待ってください」
何故か慌てた様子でわたわたと青年(のカテゴリーにもう入れてしまうことにした)は手にもっていた器をカタンとテーブルの上に置いた。中に入っていたチャイは波打って、少しだけテーブルの上に零れる。
「運命が、なんですって?」
「運命探しの依頼だよ。時々隊商にもくるだろ依頼が」
あれと一緒だと思ってくれて構わないよ、と僕は説明した。隊商を仕切るあの黒髪の女の人は、街に着くと時々依頼を受けてくる。でも彼女が積極的に依頼を持ってくるというよりは、街がやってきた大隊商に依頼をしてくるといったほうが正しいかもしれない。どちらにせよ僕としてはわかりやすい例をだして説明したつもりだったけれど、彼にとっては違うようだった。もう目を丸くはしていなかったけれど、代わりに青年はしぱしぱと何度も瞬かせている。
「急にごめんなさいね、あたしはリファーよ。リーファって呼んで頂戴」

さてどうしたものかなと悩んでいると、それまで黙って僕の隣でフワフワと浮きながらやりとりを見ていたリーファが、長い髪を耳にかけ直しながらにっこりと青年に微笑んだ。同性の僕から見たって綺麗で華やかなリーファは、異性にはもっとキラキラとして見えるみたいだ。彼女の笑顔に嬉しそうに青年は挨拶を返す。
「あ、私はナーターンです、どうぞナタンと。あの、それで…」
「そうか、ごめん同じ隊商だからって最初に自己紹介しなかったのは悪かったね。僕は略してセト、よろしく」
そういえば基本的な挨拶もすませずに依頼の話から入ってしまったことに気がついて、僕はリーファに倣って挨拶をすませる。隊商内で見たことのある顔同士だから細かい説明はいいかと勝手に解釈してた。折角だからナタンと呼ばせてもらうことにして、ナタンは挨拶を返したあと(略して?と言われたような気もする)僕から視線を外して、リーファの方を伺う。
「すみません、私にはちょっと話が見えなくて…」
「そうねえ、急な話だものね。どこから話したらいいかしら」
ねえ、セト?とたずねられ、僕はようやくどうしてナタンが戸惑っていたのかを理解した。そう言えば僕はナタンにあって開口一番、運命の捜索を頼んだものだから、事情も何も知らないナタンはなんの事だかさっぱりだったんだ。やっぱり受ける依頼の詳細は普通は聞きたいものだよね。
僕は順を追ってナタンに説明を始めた。
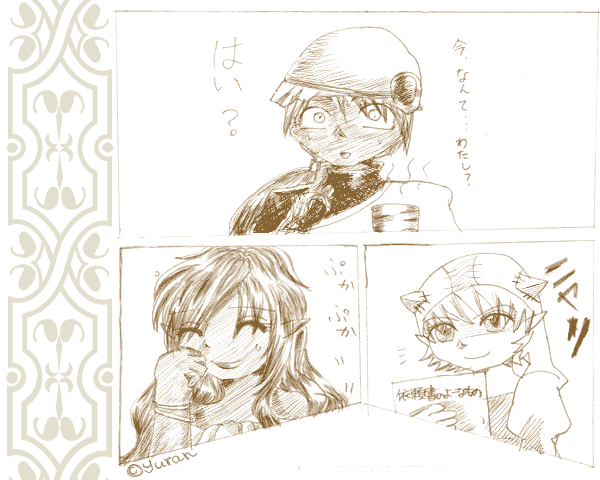
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


始まりは、道端で街の女の子相手に歌を披露したことからだった。
「イマイチね」
「え?」
ため息とともに告げられた女の子の言葉が理解できなくて、僕は聞き返した。僕よりも幼くて背も低い女の子は、それでも僕を見下すような視線を投げかけ鼻で笑う。
「それじゃ報酬はあげられないわ」
なんだか「ヨウチ」なのよあなたの歌。つまんない。
肩をすくめる仕草をすると、そのまま彼女はどこかへと去っていった。彼女は、僕が道端で歌の練習をしていたら「歌を私のために歌ってくれ」と依頼してきた女の子だった。
報酬は渡すと言われたけれど、彼女は僕の歌を聞いてさっきの一言以外何も僕には与えていない。別に、報酬を欲しくて僕は歌を歌ったわけじゃなかったから、報酬をもらえなくたっていいんだ。僕は歌が好きだから歌うし、歌うからには聞いて欲しい。それだけのために詩人をやっているのだから、無報酬であっても問題ない。だけど彼女の一言は大問題だった。
「ツマンナイ…?」
女の子が呟いた言葉を繰り返す。それはとてつもなく恐ろしく、痛々しい言葉だ。つまらない。もう一度心でその単語を繰り返すと、魂が凍りつくような感覚さえしてくる。つまらないということは、退屈という事だ。退屈ほど恐ろしいものはない。つまらなくて退屈な歌を、一体誰が聴いてくれるというのだろう。
これは由々しき事態だぞ、と僕は自分に言い聞かせた。
こんな恐ろしい事態があるだろか?いや、ないと反語を使って強調するほど僕はこの事態を重くみている。
「落ち込んだ」
言葉にしてみると、尚更気分が落ち込んだ。言葉の力はこんなにも偉大だ。大昔大岩であった頃の僕は、この偉大な言葉の力無しにどうやって生きていたのだろう?そもそも大岩だった頃の僕は生きていたといえるのだろうか。おっと話がずれてしまった。肝心なのは岩だった頃の僕が生きていたかそうでないかじゃない、僕が今まさにぶち当たってる肝心な事は、僕が落ち込んでいるという事だ。
かつてこんなにも僕を落ち込ませた事はあっただろうか?いや、ない。あるはずがない。反語だけじゃ物足りないので今度は更に一言付け足して強調してみると、尚更今までなかったような気がしてきた。
ということは僕は今、自分のジン生の中で史上最大の落ち込みに立ち向かわなければならない状況にあるということだ。
「僕の歌って、そんなにつまらない…?」
いや、そんなことはないはずだ。僕の歌を面白い、素敵だと言ってくれる人たちだっている。でもあの女の子の言葉は、そのヒトたちの言葉よりとても重くつめたくて、僕の心にずっしり沈み込む。
こういう時こそ、歌えばいい。つまらなくない歌だって僕は歌えると、僕はさっき歌った歌とは別の歌を口ずさもうとする。
「っ……」
大きく息を吸い込んで、いざ歌詞を口にしようとするけれど…どういうことだろう。まったく歌詞が浮かんでこない。いつもだったら目につくもの全部を歌詞にしてメロディに乗せていたのに、頭の中は真っ白だった。
変な歌だとヒトに言われたことはある。面と向かってなんだその歌はと怒鳴られたこともある。ヒトによって感覚は違うからしょがないかと、思ったことは一度や二度じゃない。ただ、子どもに「つまらない」と言われたのは初めてだった。パペットを使って劇調に物語を歌ってみたり、踊りながら歌ってみたり、そういう風に歌う僕の歌はいつも子どもに喜ばれていたのに。なんとなく、誰に評価されなくても自分の歌は子どもには受け入れてもらえると思ってた。嘘をつかない、もしくは嘘をついたってわかりやすい彼らの感想はいつだって率直で、だからこそ「おもしろい歌だ」と評価されるのは嬉しかった。なのに。
「どうしよう…」
あの子の言葉が頭をよぎって、歌がうまく作れない。歌詞が思い浮かんだと思ったら、ひょっとしてこれは、あの子がいうようなつまらない歌なんじゃないかという考えが一緒に湧き出てメロディにのる前にバラバラと崩れてく。僕が歌うのはもっぱら自分で作る歌だったから、歌をうまく作れないということは即ち歌を歌えないことを意味する。
歌えない詩人…それはものすごく意味のない存在だ。歌わない詩人ならいいさ、いつ歌うかだなんて個人の自由だもの。落ち込んだ時嬉しい時好きな人にあった時、気分の乗った時に好きなだけ歌えばいい。僕は個人の意思は、集団行動の中であったって多少は反映されるべきだと思ってる。だから歌わない詩人の存在はいい。
でも歌いたいのに歌えない詩人はどうだろうか?果たしてそこに存在意義はあるのか?切れない包丁、底のない鍋、何故か思い浮かぶのが詩人とは全く関係ない調理器具だけど、とにかくそれぐらい意味のない存在じゃないか!
「困った……」
僕は今、盛大に困っていて、それでいて落ち込んでいる!
誰かこんな僕を助けてくれてもいいんじゃないか?助けて欲しい時は助けてくれと主張すべきだ。自分でどう解決したらいいかわからない時は尚更そうさ。周りを見渡すと自分の問題を自分だけで抱え込んで考え込んで、頭の中の思考の糸がぐちゃぐちゃにこんがらがっているヒトがあちらこちらにいるけど、そんなのどう考えたって時間の無駄だ。力になってくれそうなヒトに助けて欲しいとお願いすれば、案外問題はあっさり解決したりする。
じゃあ助けて欲しいのに相談相手が不在中、もしくは助けてと言える相手が周りにいない、そういう時はどうするか?答えは簡単、相手が見つかるまで探せばいい。もしくはこれみよがしに主張すればいいんだ。意外と誰かかしら助けてくれたりする。渡る世間に魔物はいない。
僕はその場にがっくりと膝をついてみた。僕の顔はヒトからみると喜んでるか悲しんでいるかわかりづらいらしい。言われてみればヒトが浮かべた笑顔と僕の笑顔(のつもりの表情)は大分違う気がした。けれど、このポーズなら傍目からでも落ち込み様が十分伝わるはずだ。
「あら…どうしたの?」

ほら!早くも誰かが引っかかった!
おっとこれだと言い方が悪いかな。麗しの救いの女神が(声と口調からして、話しかけてきたのはきっと女のヒトだ)、ジン生に行き詰まり息をつまらせた哀れな詩人に手を差し伸べた…よし、こんな所でどうだろう。表現方法に納得がいったところで、僕は視線を地面から声の主へと移す。この表現がヒトにとってつまらないかどうか今は考えたくなかった。
声の主は予想を裏切らず女性だった。
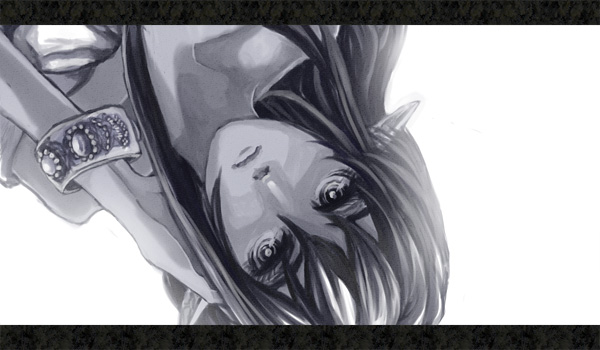
硬くて真っ直ぐで白い僕の髪とは正反対に、柔らかに波打った夜の色の髪をしている。日の光を反射してるそれは艶やかで凄く綺麗だ。瞳も同じ夜の色で、肌は日に焼けた色をしていた。どんなに頑張って日に当たっても僕の肌はそういう色にならないから、少し羨ましい。僕と同じ尖った耳をしているから間違いなくジンだ。沈んでいる僕の気も知らないで(というのは僕の完全な言いがかりだけど)フワフワと地面から浮いている。見た感じ僕よりも年上に見えるけれど、ジンだから見た目なんてあてにはならない。
全く見知らぬヒトではないけれど、親しい間柄でもない相手だ。同じ隊商に属している旅仲間で、つまり今の所それ以上の関係性がない相手。そうだとしても、そんな事はたいした問題じゃない。昨日の敵は今日の友、隊商の仲間は心の友っていうじゃないか。今思いついた名言を心の中で唱えて、僕は早速行動に取り掛かる。
僕はできるだけ悲しみの表情をうかべようとした。けどうまくいかない。やっぱり顔の筋肉を動かすのが苦手だ。岩のようにかちんこちんに表情筋が固まっているわけではないけれど、思ったような動きをしてくれない。特にそれを不満にも不便にも思った事はなかったけれどその考えは改めた、ヒトの気を引くのには向いてないやこれ。僕は早々に表情を作るのを諦めて、代わりに近づいてきた彼女の腕を逃がさないようにがっしりと掴む。
「助けて欲しいんだ」
「助けてほしいって?」
僕の切実な願いに、彼女はぱちくりと眼を瞬かせた。まったくその気がない相手だと大抵は目を逸らして「すいません急いでますんで…」と断ってくるか、「困ります」とでも言って逃げ出すか。このヒトは視線を逸らさずに僕の願いの詳細を尋ねてきた。この反応は脈ありだぞ。
「僕は略してセトだよ。君と同じ隊商で詩人をしてる」
セツィアツィルトという名前は長いし舌を噛みづらいから、僕はいつもこうやって省略した名前を名乗る。今すぐ相手が逃げ出す事はしないとわかれば、何も急ぐ事はない。僕はまず最初に自己紹介をした。いくら同じ隊商に属しているからといって、全員が全員の顔と名前を一致させているわけじゃない。何せ大所帯の隊商だ。同じ職業同士だったら多少は交流もあるけれど、違う職業だとなかなかそうもいかない。
「あら、あたしはリファーよ。じゃあ私の事はリーファって呼んで」
僕が腕を離して代わりに手を差し出すと、リファーもといリーファはにっこりと微笑んで手を握ってくれた。感じがいいヒトだ。おまけに美人さん、これはいい出逢いをしたぞと僕は内心でガッツポーズをとった。
「早速だけど助けて欲しいのは…」
「ちょっと待ってね、内容を聞いてもあたしが助けられるとは限らないわよ。それでもいい?」
喋り出した僕を手で制して、少し困ったように眉を下げて問われる。勿論それでも構わないよと返した。きちんと前置きをする彼女は、助けてと言われればなんでもホイホイ聞いてしまう僕の甥よりずっと賢い。ますますいい出会いをしたぞと確信する。
僕は切れない包丁、底のない鍋、それと同列の歌えない詩人の苦悩を打ち明けた。世の中やたら愚痴っぽいヒトっているよね。そんなにマイナスばっかり吐き出してどうするんだろうと僕は思うけれど、今だけなら愚痴っぽいヒトの気持ちがわかるな。この話をした瞬間って、胸がスッとする。何かが解決するわけでもないのにモヤモヤを外に吐き出すのは、こういう爽快感を味わいたいんじゃないだろうか。
「歌、ねえ…あたしは奇術師だからいいアドバイスはできないわ、ごめんなさい」
「奇術師なのかい?」
その事実を知るまで、僕はなんとなく彼女は踊り子なのではないかと思っていた。動きやすそうな服装に褐色の肌に映える金色の腕輪は踊り子っぽかったし、くるくると回ったら耳からぶら下がった赤い耳飾りと長い黒髪が綺麗に弧を描くような気がして、僕としては奇術をしている姿よりも簡単に想像できる。でも実際は奇術師である彼女にそんなことを言うのは失礼かな。僕は予想を口にするのはやめ、かくして予想職業:踊り子の結果が外れだった事は僕だけが知る事実のひとつとなった。
「奇術師なら同じ芸人仲間じゃないか。同じ芸人仲間のよしみとして、ねえなんでもいいんだ!アドバイスをくれないかい?」
「そうねえ…」
困ったように彼女は呟いて、その端正な顔を僅かにしかめながら考え込んだ。数秒した後思いついたように伏せがちになっていた顔を上げて、
「歌えなくなったって、歌う気分じゃないってことかしら?それとも歌いたい歌がなくなったって事?」
「歌う気分じゃないっていうか…歌がうまく作れないんだよね」
具体的な方針を打ち出すためにはまずは根本から突き詰めていく、なるほど、悩んでいる当人よりも他人の方がよっぽど問題に対して現実的に取り組めるもんなんだね。
「僕、その日あった事とかから歌を作るんだよ。だけど最近歌を作っていて、なんだかマンネリとした歌が多いというか、ヒトにウケない歌しか作れないというか…そんな気がして」
女の子に「つまらない」と歌を評されたことをちょっといいたくなくて、僕の言葉は根本の原因から少し遠回りな回答になる。
その日の天気、出会ったヒト、美味しいご飯、綺麗な花、初めて見たもの、そういう僕がいいなと思ったものを普段歌ってる。でもあの女の子の言葉が突き刺さっている今、作る歌全てがつまらない気がしてならない。
隊商の中には、僕と同じ様な詩人が何人もいる。そのヒト達が作る歌や歌う歌は、すごく素敵なものが多かった。そのヒト達の歌う歌に比べると、確かにあの女の子がつまらないというような歌しか僕は歌えないし作れない気がしてくる。そう思うと全然、歌詞もメロディーも浮かんでこない。あんなに歌を作るのも歌うのも楽しいと思っていたのに、急に僕は歌うことが苦痛に感じるようになった。彼らが歌う歌を砂漠の夜空に輝く大きな道標の星に例えるなら、僕の歌なんて道端に転がる石クズのよう。
「そうねえ…なら気にいる歌が作れるほどの出来事がない日が続いてるんじゃないかしら」
「………それだ!」
彼女の言葉に納得がいって、僕は自分の右の拳を左の手の平にぽんと打ちつけた。そういえばここしばらくずっと、僕はだらだらしっぱなしだった。怠けていたから特に面白いこと、それこそいい歌にできるような出来事がなかったんだ!だから、あの子はそんな僕の歌をつまらないと感じたに違いない。きっと凄い出来事に出会えれば、僕も凄い歌が作れるさ。
「じゃあ何か歌に出来そうな出来事を探しにいかないと!」
僕のこのもやもや全てを吹き飛ばせる方法があるのならば試さずにはいられない。じっとしていられなくて足踏みをしながら身体を左右に動かすと、リーファは「あらあら落ち着いて」と軽く手で制した。
「そうねぇ、例えばどんなことがいいのかしら?」
彼女の問いに、僕はうーんと唸って見せた。隊商の他の詩人達が作る歌にも劣らない、あの女の子にもつまらないと言われないような、すごい歌を作るためのインスピレーションを与えてくれる出来事が必要だ。ちょっとしたいい事とか事件とかじゃ、その役割を果たしはしないだろう。
「…そうだなぁ、すごく感動的な出来事を期待するね!そのほうが歌にしやすいしインパクトがあるし、きっとウケがいいよ。生き別れの兄弟や親子が旅先で運命的な出逢いを果たすとか、そういうの!」
とてつもなくいい例が浮かんで握りこぶしを胸の前に振りかざして熱く語れば、リーファは一瞬だけ驚いたように目を瞬かせ、それからすぐになんでもないかのように優雅に微笑んだ。
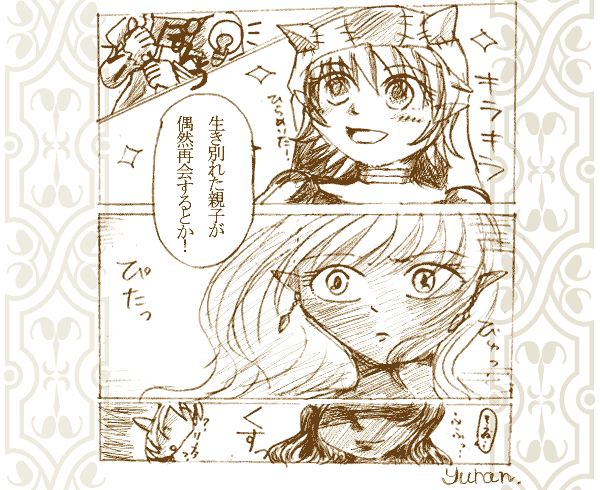
「…そうねえ、そういうの素敵よね」
「まあ、そうそう都合よく出会ったところを目撃できるわけがないとしても、とにかくそれぐらい運命的な出来事がみたいな!どこに落ちてると思う?どうやったら見つけられるかな?あれかな棒を立てて倒れた方に進むとかそういうのだと見つけられたりするとおもう?普通にやっちゃあれだから、三回回って運命とか叫んでから倒したほうがそれっぽいかな」
たたみかけるように僕が言うと、彼女は小首を傾げ「それじゃあちょっと当てがなさすぎないかしら」と返した。…うん、僕もちょっと無茶があるかなあとは思ってた。そうは言われても、他に良い手が思いつかない。とりあえず木の棒を探そうと僕が道端を見回していると、ポツリと彼女が呟く。
「運命的ね…そうねえ、運命って星の巡り合わせって表現するわよね」
「?」
都合よく木の棒を見つけて拾い上げた僕は、彼女の言葉に首を傾げる。リーファはにっこりと微笑んだ。
「こっちの方が、木の棒より運命に出会えるかも」

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
「というわけで、君に運命を探してもらいたいのさ」
女の子のくだりを省いて、リーファと出会い星読みに運命探しを依頼する事になった経緯を説明をし終えると、ナタンは「はぁ」と気の抜けた相槌を返してきた。
「…ということは私に行き着いた経緯は」
「木の棒」
これさ、とナタンの問いに僕は手に持っていた棒を振った。木の棒に運命探しの全責任を任せるよりは星読みに頼んだ方がいいんじゃないかとリーファに言われたけど、そもそもあの場に星読みはいなかったから最初の一歩は木の棒に頼んだんだ。
「こうやって…」
木の棒を地面に対して垂直に立てて、ぱっと手を離す。からんと棒は音を立てて床に転がった。示した方向は木の椅子に座っているナタン。
「棒の先が示した方に向かってきたら、星読みの君がいたってわけ」
「はあ…。あの、別に僕の星読みとしての能力評判を聞いたとかではなく」
「木の棒」
木の棒が示した先でナタンを発見した時は、飛び上がるほど嬉しかったね。僕の木の棒が、星読みを探し当てた!僕ちょっと星読みの才能があるかもしれない。どことなくナタンはがっかりしているようだったけど、僕は気にしないことにした。
「…進んだ先にいなかったら、どうするつもりだったんですか?」
「そりゃ見つかるまで転がすだけさ」
「……」
何故か沈黙するナタンに対してリーファは「ジンって気が長いのよ」なんて言いながら笑っていた。
「じゃあ早速運命を探してよ」
「あの、」
詳しい事情がわかったなら依頼を受けてくれるだろうとたかを括って話を進めると、慌てた様子で僕の言葉を遮った。
「申し訳ないんですが、私そういった類はあまり」
そういうのを占ってもらうのは好きなんですけど、と付け加えられる。衝撃の事実に、今度は僕が目を丸くした。
「そんな立派な杖を持っているのに?」
「え、これですか?この錫杖は…」
「あ!大丈夫だよタダでとかいわないさ。なんなら商人がやるみたいにちゃんと依頼書とか契約書とか書いて…」
「そ、そうじゃなくて…」
もしかして無報酬で占いを依頼されるのが嫌なだけかと思って、僕は人差し指を立てながら説明する。のに、まだナタンは戸惑っているみたいだった。一体何が不満なんだろう。僕は首を捻る。
「あれ、星読みでいいんだよね君」
隊商が砂ばかりの地を歩いて目的地にたどり着くためには、方角を正しく知る必要がある。星読み達が集まって次の目的地に行くまで道筋を確認する事は、旅の最中何度もあった。定期的に行われているらしい星読みの集まりの中に彼もいたのを見かけた事があるから、てっきりナタンは星読みだとばかり思っていたんだけれど。
「星読みですけど、運命を見つけるような事はできませんよ。先見ができる方は同業者にいますが、私にそんな能力は…。私はこの錫杖を使って」
「僕のさっきの木の棒みたいに転がして道を調べるんだろう?」
「違いますよ!?」
正しい答えを口にしたつもりなのに、ナタンには全力で否定された。彼が持っている立派な錫杖は、てっきりそういう時のためにあるのだとばっかり思っていたから意外だ。けど、よくよく錫杖の形をみれば納得する。
「そうか、転がしづらいもんね…」
「そういう問題かしらねえ…」
僕の呟きにリーファは同じ様に呟いた。そういう問題じゃないのかな。この形状だと絶対にころんと転がせることはできないと思うんだけど。
「これで星の位置を見るんです。道の案内はできますけど、運命の道は…」
僕らのやりとりに苦笑いを浮かべながら、ナタンは正しい答えを口にする。ほら、ここに星図がついててですね…と錫杖をもって説明を始めたけれど、僕は星図に関しては特に興味が無いので「興味ないや」の一言でその説明をぶったぎった。
「そうか、転がして探すわけじゃないのか。まあいいさ。それより占えなくてもこの際いいから、運命的なものを探すの手伝ってくれないかな。ここであったのも何かの縁だし。一人より二人、二人より三人で探した方がいいだろ」
「運命的なもの…ですか。そ、それは運命の人との出逢い、とかですか?」
「…なんだいその運命の人って。そんな人いるの?」
突然目を輝かせたナタンの問いに、僕は問い返す。
「私は家の占い師に、旅にでた先で運命の人に出会えると言われたんですよ」
「あら素敵ねぇ」
ロマンチックじゃない?とリーファに同意を求められて僕は頷いた。確かに、歌の題材に出来そうなぐらいロマンチックだ。だけどふとある事に気がついて、ナタンに問いかける。
「どういう運命の人だい」
「え、どういうって…」
「運命なんていっぱいあるじゃないか。曖昧すぎてわからないよ。宿命のライバルかもしれないし、人生の師匠かもしれないし、どういう運命の人だって言われたの?」
「…いえ、そこまで詳しくは言われませんでしたけど」
戸惑ったナタンの回答に、僕はなるほどと頷いた。
成る程、その占い師は随分曖昧でふわふわとした道標を出したもんだね。僕だったら占い師にそう告げられた時点で、詳細を聞き出してメモしちゃうけど。それとも曖昧な道標しか占い師は出せなかったんだろうか。
「よし…じゃあ君の運命の人を探そう」
「え」
「あら、おもしろそうねぇ」
僕ががっしりとナタンの右手を両手で握って宣言する。リーファも僕の提案に乗ってくれた。善は急げだ。こんなところでゆっくりなんてしていられない。折角の歌のネタになるような「運命」というものが転がっているかもしれないというのに、放置なんてできない。
「あれ…待ってください、振り出しに戻りますけどその運命の人はどうやって探すんですか?先ほども言いましたけど、私には運命を探すような占いは…」
「もういっそこの木の棒で…」
「結局木の棒ですか!?」
悲鳴のような声を上げるナタンを無視して、僕はもう一度木の棒を転がした。
「こんなところを探して、運命の人は見つかるのかしら」
僕とナタンの二人が露店にある大きな壺を覗き込んでいるのをみながら呟くリーファに、僕は運命の人はどこに潜んでいるかわからないよ、と答えた。壺の中は想像以上に音を反響させて、自分で自分の声がうるさいなと文句をいうと、リーファが笑う。
「ひょっとしたら台所の隅とか、壺の中とか、寝床とかに潜んでるかもしれない」
今度は壺から頭をだして、僕は運命のヒトの居場所の可能性を口にした。リーファは変わらず綺麗な笑顔を浮かべながら、
「寝床だったら不審者じゃないかしら」
「斧とかもって息をひそめて今か今かとナタンを待ってるかも…」
「それ殺人鬼みたいなんですけど!?」
僕と同じ様に他の壺に顔を突っこんでいたナタンは、懸命にも顔を壺から出してから悲鳴を上げる。
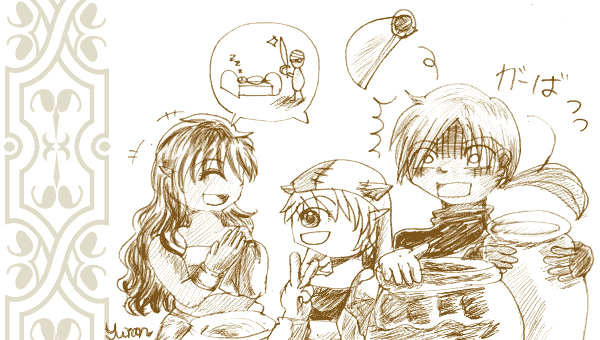
「命をそこで終わらせるのだったら、確かに運命の人だけどねえ…」
「さりげなく怖いこと言わないでください!」
僕の言葉に付けたしたリーファの言葉に、ナタンはさらに声を上げた。僕としては歌にしやすい出来事だったら別に運命の相手が殺人鬼でも義賊でもなんだっていいんだけど。ああ、でも折角一緒に探してくれている彼の運命のヒトが、殺人鬼っていうのは流石に不憫かな。ウケも悪そうだ。出来れば彼の運命のヒトは殺人鬼ではないことを祈ろう。
「あの、やっぱり占いをやる方に占ってもらった方がいいのでは」
僕より一足先に壺の中の捜索を終えたナタンが提案して来たが、僕は首を振った。
「探して占ってもらうの面倒くさ………先に依頼を受けてくれた君に失礼じゃないか」
「今面倒くさいっていいませんでした?」
「気のせいだよ」
僕は探索を終えた壷の淵を軽く叩いた。運命の人は入ってはいなかった。当たり前だったかもしれないけど、店の脇に置いてある壷なんて食料とか水とか油とか空だったりとか、そんなありきたりなものしかない。露店の店主が「商品に何をするんだ」と訝しげな視線を投げ掛けて口を開いたけれど、リーファがにっこりと笑うとしまりのない笑みを返すにとどまった。美人って笑顔に特殊効果でも付加されているんだろうか。便利だなあ。
「…もっと人が多い所で探した方がいいのかなあ。看板でももってさ、『ナタンの運命の人募集中!』みたいにしたら寄ってくるかも」
「それはちょっと…」
「沢山集まったら困るわよ?」
乗り気じゃないナタンと、リーファの意見を聞いてうんまあ確かにそうだと僕は浮かんだ案を取り下げる。三人で探せばもっとあっさり見つかると思ったのに、なかなかそれっぽいのがみつからないものだ。
案外見つからないものだね運命って、と僕がぼやくと探してもなかなか見つからないから運命っていうんじゃない?とリーファに言われて、そうかそういうものなのかもしれないと納得した。
「……君ってさあ」
納得はしたけれど、僕は今凄く運命を欲して焦れていた。こんな気持ちになるのは僕だけなんだろうか。とりあえず休憩しようと露店で買ったアイランを口にしながら、道ばたで僕は問いかけた。
「運命の人が見つからなくて、つまらなくない?」
ついさっき運命を探そうと決意した僕とは違い、旅の開始時期から運命の人を探していたナタンはどうなんだろう。この隊商が旅を始めてからもう一年以上たつ。ナタンはなかなか出会えない事に焦ったりしないんだろうか。
「え?そんなことないですよ?旅自体が楽しいですし」
運命の人探しが一番の目的なわけじゃないですしね、と意外や意外、けろっと答えられて僕は拍子抜けした。
「旅は色々学ぶ事も多いですし」
「でも運命の人見つからないんだろう?」
「なかなか出会えないのもロマンチックじゃないですか!」
眼を輝かせて熱く宣言するナタンに、そんなものなのかなと僕は思案した。僕だってなかなか見つからない方が燃える時がある。例えばそこらの子供達の遊びに混ぜてもらってやるかくれんぼ、あれは巧みな子供達のかくれんぼ技術に翻弄されながらも、必ず見つけ出してやろうと燃え上がる。さながら気分は砂漠のハンターだ。
ただ早く見つけたいものはある。例えば今飲んでるアイラン。喉が渇いたから僕は今すぐ飲みたいと思っていて、運良くリーファがアイランを売っている店をすぐに見つけてくれた。今の僕は、いわば喉の乾いたヒトなんだ。はやくいい歌の題材となる運命をみつけて、この喉の渇きを癒したい。
「リーファはどう思う?」
「あたし?」
「リーファも何か探してるものとか、欲しいものないの?それが見つからない時って、イライラしない?」
「そうねえ…」
僕の問いかけに、綺麗な唇に人差し指を当てて少し考える。数秒の後その指先を唇から離して僕へと向け、告げた。
「…そうだわ、セト。試しに歌ってみて」
「え?…でも僕は運命のヒトが見つからないと、今はいい歌が作れないと…」
「ならさっきあなたが言った、生き別れの親子が出会った事を思い浮かべて歌ってくれないかしら」
「うーん…」
もしかして、問いをはぐらかされたんだろうか。うまく歌えないって言ってるのに、と少々彼女の提案を不満に思いながらも「歌ってみて」と頼まれると僕はどうしても断れない。それは僕が甥のように頼まれると断れない体質だからというわけではなくて、僕は歌うことが何よりも好きで、機会さえあればいつだって自分の声で高らかに浮かんだ言葉を歌い上げたいと思っているからだ。
それはあの女の子に「つまらない」と評された今でもやっぱり変わらない。変わらないんだけど、あの子の声が頭から消え去るわけじゃないんだ。
「…星降る砂漠の地…」
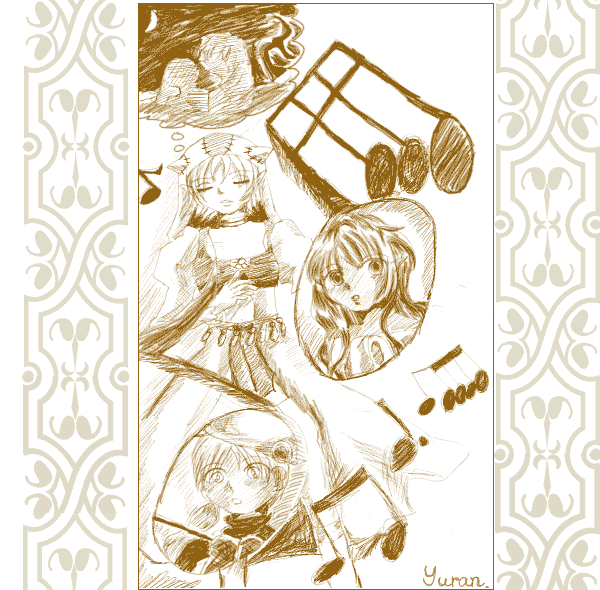
僕は慎重に言葉を選んで歌い出した。女の子に歌って、つまらないと言われたのは僕がいつも歌っているような、難しい言葉を使わずに簡単な言葉を使う歌だった。だからそれとは正反対の、古い言葉とか難しい言葉とか、そういうのをいっぱい使うように考えて歌う。
ひと通り僕が「生き別れの親子」の歌を歌うと、ナタンとリーファはパチパチと手を叩いてくれる。素敵ね、素晴らしいですと褒められて僕は嬉しい…はずなんだけど、なんだろう、もやもやが晴れない。ナタンが言葉が綺麗でどうのこうのと、歌詞も褒めてくれるけどそう褒められれば褒められるほど僕の内心は複雑だ。今歌った歌に、僕はあまり想いを込めて歌っていない。気に入られる様な歌詞を考えて歌うことに一生懸命で、正直どんな歌を今歌ったのかも自分ではよくわかっていなかった。僕が折角の二人からの賞賛に押し黙っていると、リーファは優しく微笑んだ。
「セトがナタンの『運命の人』を探したいのは、歌の題材が欲しいからなのよね」
「そうだよ。リーファが言ったんじゃないか、唄が上手く作れないのは、歌をつくりたいほどの出来事がないからじゃないかって」
リーファが告げた言葉は僕が問いかけた内容の答えじゃなくて、少しガッカリした。質問を質問で返すだなんてずるいじゃないか。そんな僕の内心の憤慨をよそに、彼女は言葉を続ける。
「そうねえ、確かにそうだわ。でもさっきからあなた他人がすごいというような歌を、っていってるけれどそれでいいのかしらって思ったの」
「………どういうこと?」
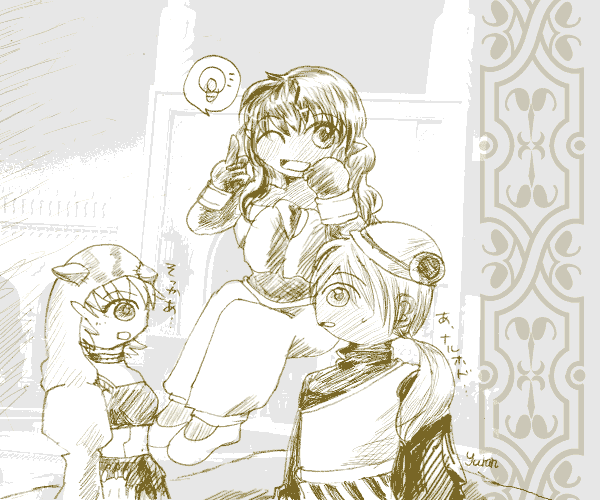
ね?と問いを投げかけるように言われて、僕は眉根を寄せた。これぐらいの表情の変化なら僕だって出来る。不可解な意志を表そうと僕が作った表情は、僕の意図通り彼女に伝わったようで、さらにリーファは言葉を続ける。
「いいものを作ろうと思いすぎてかえって普段通りの力がでないことってあるものよ?」
「でも気合いれてやろうって思う事は誰だってあるだろう?」
「気合いを入れるのと、他人の評価を気にするのはまた違うわよ」
あなたが歌の中で一番に気にするのが評価なんだとしたら、それでもいいかもしれないけどと彼女は付け加える。
「うーん…」
言われてみれば確かにそうかもしれない。僕の今言っている「いい歌」は確かに人にウケる歌の事を示している。普段だったら僕は他人の運命なんてどこに転がってるかよくわからないモノをわざわざ探しに行って、いい歌をつくろうなんて思わない。日常に転がってるモノを題材にして歌を作るのが僕だ。僕はあの女の子のたった一言、「つまんない」に振り回されているのか。
「人にみせる限り、評価されてなんぼだと思いますけどねえ」
何気なしにこぼしたナタンの言葉に頭に来たわけではないけれど、多少は腹がたったので、僕は彼のもっていたアイランをひったくって一気に喉に流し込む。
何するんですかああ!?と叫ぶナタンの言葉は無視した。どうせ依頼の報酬の一部として僕が奢ったアイランだ。文句を言われる筋合いは……あ、報酬の一部だったなら僕が飲んじゃ駄目なのか。まあいいや。リーファはというと、苦笑している。感情論でしかないけれどねと付け加えられると、成る程ナタンの言葉は現実的で別に嫌みで言ったわけじゃないんだろうなという気になってきた。
「そうだね、僕なんだか気にしすぎただけなのかも」
隊商には沢山の詩人がいる。隊商は色んな所に行くからこれからもきっと、詩人は増えるかもしれない。その度にきっととても素敵な歌を歌う人が現れるんだろう。僕なんかじゃ歌えない、凄く素敵な歌をすごく綺麗な声で歌って、みんなに評価されるに違いない。そして僕だけ評価されないってことも十分あり得る。
だからといって僕がそういう歌を真似したって同じように歌えるわけじゃない、その人たちだからこそ歌える歌なんだ。僕らしさを無視して歌を作って評価されて、それの何が楽しいんだろう。いい歌を作るために題材を探すわけじゃない。出来上がった料理を想像しながら具材を探すのもいいんだろうけれど、僕はそういうスタイルの詩人じゃなかった。色んな具材をみつけて、どんなのができるかなとわくわくするのが常だった。
そう、なんか、こういうのは僕らしくない。評価されるために歌うのは別に悪いことじゃないだろう、ナタンがいうように人にみせる限り評価されてこそという考えも確かにあるのだから。でも僕にとって歌う事は、それが一番な訳じゃなかった。
「…よし、運命の人探しはやめよう!」
「え?私の運命の人は…」
宣言した僕にナタンが戸惑った声を上げる。そんな彼の肩の上に僕はそっと手を置いて、目を伏せて告げた。
「運命の人は心の中にいるんだよ…」
「ええええ!?」
うまいこと言ったつもりだったのに、どうにもナタンにはウケが悪かったようだ。悲鳴のような声を上げたあと、それじゃまるで死んだヒトみたいじゃないですか!?とか文句言ってるけど僕はスルーした。念を押す様にぐっとナタンの肩を掴む力を込める。
「いいかい、会いたいと思うなら会えるさ、君がそう望めばね」
「というか、先に探そうって言い出したのセトさんですよね!?」
「ううん、ジン生はうつろいやすいものさ…」
まだ納得しきれていない様子のナタンだったけれどまあいいや。他人の評価も意見も気にしすぎちゃいけないからね。僕のスランプの原因は結局それだったんだろうから。今の僕は、なんだって歌えそうな気分だった。ようするに、細かい事は気にするな。好きなものは好きなようにやれってことだ。
「あ、ちゃんと二人にお礼はするよ!今夜おいしそうなお店で宴でもどうだい?歌も披露しちゃうよ」
「あら、歌えるようになったの?」
「うだうだと悩んでないで、まずは歌う事にしたよ。『ナタンの運命のヒト予想図』なんて歌ってみようかな」
「なんだかさっきの話の流れからして嫌な予感しかしない歌なんですけど…」

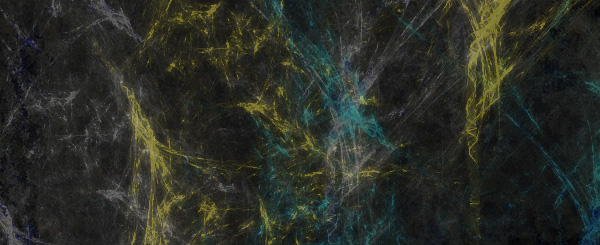

不安そうにナタンは言うけれど、気にしない。
そうそれが僕のスタイルだ!
僕は歌を口ずさみながら、二人の腕を掴んで歩き始めた。

