未来の声を運ぶのは…
執筆:ギルゾア(音羽)
挿絵:カーミル(秋吉本家)・ポストーチ(ムツホシラ)・アスラン(Nasato)
その一言は
親切だったのか、迷惑だったのか、
それは誰にもわからない…
未来の声を運ぶのは…
その日、踊り子の少年は人気のないさら地に天幕を張ろうとしていた。
行商の踊り子は行く先々の街で踊りを披露し、腕前によっては権力者の前で舞い、富を得るチャンスがある。
少年はこの街で鏡のように舞う双子の踊り子として名を広め、数日前、彼らは街の権力者への謁見を許されたのだった。
今建てている天幕はその練習用にと思い、建てているのである。
未来への期待を乗せて、作りかけの天幕の柱が天へ伸びていた。
「そろそろ倒れますよ」
声がかけられるまで。
少年がその声に手を止めたとたん、派手な音を立てて、柱は地面に倒れた。
少年は声の方向を振り向く。
そこには一人の男が立っていた。
褐色の肌に映える銀髪。
細い体にまとわれた闇に溶け込みそうな黒い衣に、金色のアクセサリーが品よく添えられている。
妖しげな微笑みを浮かべると、背後のマントが軽く揺れた。
…記憶にある。
確か前の商隊でも見かけた、どこか近寄りがたい雰囲気を持った…呪術師、だった気がする。
「なんだよ、いきなり」
むっとして睨み付けるが、男は表情を崩さない。
「練習ですか?」
広がった袖から細い指をのぞかせ、口元にあてがった男の表情が、どこか自分を小馬鹿にしたようにみえた。
「別に。いつどこで練習しようがおれの勝手だろ」
体の向きを戻してしゃがみ込む。
特に親しい間柄の人間でもない。
「辞めたほうがいいですよ。今日は日が良くない。このあと…」
「…うるさいなぁ!」
少年は振り向かず、口調だけを強める。
倒れた柱を立て直し、たたまれた布を広げようと手をかけた。
「なんだ、さわがしいな。賊か?」
地面を踏みしめる音が今度は別方向から聞こえた。
…顔を…あげたくない…
聞き覚えのある声に少年はしゃがんだまま両手を地面につきたくなった。
呪術師の男は仕事の帰り道だった。
穏やかな活気にあふれるこの街には陽の気が満ちている。
人の気を敏感に感じるこの身には、有り難い街であった。
「……?」
路地を抜けた先に広がった空き地に人のいる気配を感じ、立ち止まる。
ただの気配ではない。
近づくにつれて感じるのは、その人のあまり良くはない未来の気配であった。
見ようと思えばもう少し詳しく見ることが出来るのだが、今は見えないように制御するすべを覚えている。
…逆を返せば、制御していても見えるほど、彼に良くない相が出ていると言うことだ。
その後ろ姿には見覚えがある。確か踊り子の双子だったはずだ。
後ろ姿ではわからないが、まとう気から区別はつく。
普段ならば通り過ぎてしまうが、その時は何故か、一言告げておかねばならないような気がした。
案の定、彼は今ぴくりとも身動きせずに地面を見つめている。
間に合わなかったのか…?
呪術師は声のする方向を見据えた。
体格の良い男が立っていた。おそらく声の主はこの男だろう。
色素の薄い髪と正反対の派手なターバンが印象的だ。
羽織った上衣が風になびき、いかにも助けに駆けつけたヒーローという体だ。
まとう気が自分自身と正反対なのが、刺さるように感じられる。
「我が従僕を侮辱する賊はお前か。…ふっ、女神の慈愛を受けた俺の敵ではなさそうだな。
面倒だが従僕の管理も俺の勤めの一つ。
こうも次々仕事が舞い込むとは、女神もよほど俺の雄姿をその目に焼き付けたいのであろうな。」
どうやら自分は賊と見なされたらしい。
口調からして少年の知り合いなのだろう。
「して、お前は何者だ。
その出で立ち…なにかよからぬことをする類の輩であろう。俺の目は誤魔化せんぞ。
…いやしかし賊には賊なりの大義名分とやらがあるのであろう。
女神の慈悲を一滴お前に分け与えようではないか。
女神への懺悔…つまりお前が何をしようとしたのか、正直に話すがいい。
なに、礼などいらんさ。
砂漠の民草に女神の慈悲を分け与えるのは当然の行いだからな。
最期に俺と出会ったこと、それがお前の人生にとって至上の幸運だったとわかることだろう。」
自分とは対照的な鍛えられた四肢を大仰に動かし、男は言った。
やたら話が長いがとりあえずこちらに話が向けられているようだ。
恭しく礼の姿勢を取り、砂避けの薄布越しに口を開く。
「女神様の御慈悲を私に分け与えて下さったこと、誠に感謝致します。
私はこの少年が一人天幕を立てておりましたので話しかけた、通りすがりの身です。」
それだけを告げて再び顔を上げると、正面にいた男はやはり大仰に手ぶりをつけ、
打って変わって好意的な気を放った。
「そうか、お前は賊ではなかったのだな。疑ってしまってすまないな。
女神の加護に免じて水に流してほしい。
…しかしそうなるとアスラン、親切な御人に声を荒げるとはあまり感心できないのではないか。」
二人が同じ方向を向くと、少年は組み上げた土台にかけていた布の間から顔をのぞかせた。
「別に手伝ってくれるって言われたわけじゃないし、言われたってこれくらい自分で出来る。」
それだけ言うと、少年はぷいと天幕の奥に隠れてしまった。
呪術師は失笑し、突如現れた男はやれやれと言わんばかりに前髪を手で跳ね上げた。
「そういえばまだ名前を聞いていなかったな。
俺はカーミル・タウフィーク・ルトフという。」
呪術師はふと笑みを浮かべた。その名は人づてに聞いたことがある。
「ギルゾアと申します。」
「そうか、ギルゾア…心に留めておこう。
女神のお導きがあればまたどこかで出会うことだろう。さらばだ。」
カーミルと名乗った男は少年の後に続いて、天幕に入っていく。
一人、その場に残された呪術師…ギルゾアはどこからか手にしたカードを口元にかざし、呟く。
「その『女神の御慈悲』とやらがこの後降り注ぐと忠告したかったのですが…余計なお世話だったようですね…」
慣れないことはするものではない。
「…賊…ですか…」
そう罵られることも、疑われることも、恐れられることも、もう慣れてしまった。
女神の御慈悲…そんなものはとっくに受けることなく生きている…
見上げた空には分厚い雲がかかり、降り注いでいた光をゆっくりと遮断していく。
あたりが闇に包まれていく。
間に合わない。…いや、天幕が出来たのだから、間に合ったのかもしれない。
ギルゾアはその場を立ち去ろうと向きを変えた。
ぽすんっ!
気がつくと、『それ』は彼の腕の中に…いた。
薄い桜色がかった白い塊がぐるりと動く。
「ごめんなさいっ…あれ?」
腕の中に抱き留めたのは商隊で共に働く医師の女性だった。
面識は…ないのだが。
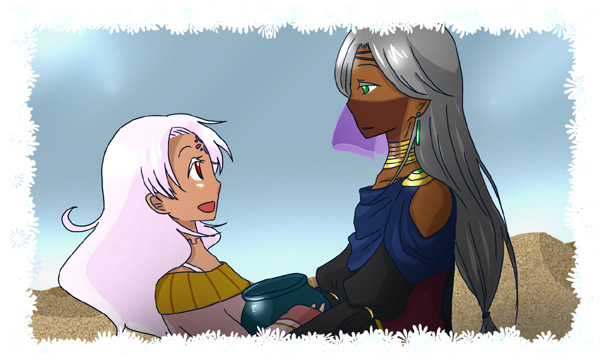
「ギルゾアくんかぁ。よかったー!あ、よくないけどっ、怪我はありませんかー…わっ」
離れようと一歩ずれた際にギルゾアのマントを踏んだらしい。
相手の容態を最初に重んじるのは職業者らしいがそそっかしいところがあるようだ。
「大丈夫ですか?」
「えへへ、ありがとっ」
抱き留め直し、彼女の姿勢を直すと、ギルゾアは一歩下がった。
「申し訳ありません。考え込んでいました。」
「先生こそ急いでました。ごめんなさい!」
よくみると彼女は腕に甕を抱えていた。
なにかが入っているのだろう。
「私の名前を…どこで?」
「先生はお医者さんだからね。商隊の人の顔と名前は覚えてるよ!
ギルゾアくんは前の商隊から要注意人物!」
満面の笑みで要注意人物と言われてしまった。
「痩せすぎだし生活不規則そうだしなんか悩んでるねっ!困ってることは先生が聞くよっ!」
道ばたで人生相談の誘いを受けてしまった。
「先生はポストーチっていうよ!ポチ先生って呼んでね!」
にっこり花のように笑うとポストーチはすたすたと歩き始める。
その後ろ姿を見送っていると、突然振り向いた彼女と目が合った。
にこりと微笑み、せっかくなので少年にあげ損ねた忠告を口にする。
「もうすぐ雨が降りますよ。お気をつけて…」
「で、結果がこれですか…」
「なんだよ!おれのせいだっていうのかよ!」
「……。」
ギルゾアのつぶやきをすかさずアスランは拾い上げた。
カーミルに至っては饒舌な口を開くかと思いきや黙り込んでしゃべりもしない。
「はいはい、静かにね。天幕はまた張ろうね!」
「そういう問題じゃない!」
ギルゾアがポストーチに雨が降ると伝えるやいなや、二人の脇にあったはずの天幕は派手な音を立てて崩れた。
中にいる二人を助け出したはいいものの、今度は雨が降り出す始末…
四人は近くにあったポストーチの医務室(本人談)に案内された。
幸運にも大事にはならなかったのだが、二人は不機嫌絶頂であった。

「このような美しい御婦人に手厚い看病が受けられるのは女神のお導きに違いないな。
運命の出会いに感謝しよう…と、いいたいところだが。」
カーミルは顔を上げ、ギルゾアを睨み付ける。
「この俺がいながらこのような事故が起こるだと。解せない。
大体お前は未来を見るのが仕事だそうだな。
何故この不始末を事前に止めようとしなかったのだ。職務怠慢…」
「うんうん、わかったから動かないでねー えいっ」
ポストーチはかまうことなく、『取れたての水』で濡らしたタオルをカーミルに押し当てる。
「うわ、雨水じゃん、それ」
「大丈夫!ギルゾアくんが濾過してくれてるからっ!」
顔を引き攣らせたアスランにポストーチはのほほんと笑った。
「まったく、この俺がいながら何事だ…今日はろくなことがないな。」
「…それ、おれの台詞なんだけど。」
『日が良くない』ってこういうことか。
…あいつの言う通り…いや、あいつに出会ってから…!
こちらを睨み付ける二人にひるむわけでもなく、ギルゾアはいつも通りの笑みを返す。
「私の仕事は『耳を傾けた人に答えること』ですので。」


ギルゾアは部屋の外へ歩いていく。
激しく降る雨音を耳に響かせながら、ギルゾアはまた一つ、微笑を浮かべた。
「未来の声はこの身に秘める方が良いのかもしれませんね…」
|