通り雨
執筆:アーリク(mio)
挿絵:シーリーン(たまだ)・リディアン(猫冶)
医者の詰める天幕に、アーリクは一人だった。案外に医者の多いこの隊商では、こんな日は珍しい。
朝に稽古で怪我をした護衛をみて以来、患者も一人として現れない。
まあ、こういう日もあるだろう。何もないのは、悪いことではない。アーリクは、大人しく本でも読んでいようと、同僚に借りた医学書を開いた。
「邪魔するで」
本を読み始めてから、どれくらい経っただろうか。
突然かけられた声に、本に没入していた意識が現実に舞い戻される。思わず本を閉じてしまった所為で、どこまで読んだのか分からなくなったのに気づき、しまったと呟きが洩れた。
乱入者はお構い無しに、天幕の奥まで入ってくる。
「リディアン」
来訪者の顔を見て、内心ぎょっとする。いつも明るい笑顔を振りまいているリディアンの表情が、ひどく暗かったからだ。
普段の元気さが完全に鳴りを潜めたリディアンの姿を見て、病気でもしたのかと職業柄心配になる。そもそも、彼がこの天幕にやってくることは殆どないのだ。

ふとアーリクは、リディアンの全身が濡れていることに気づいた。
「どうした、泉にでも突き落とされたのか」
飛べるジンがずぶぬれになる状況が想像つかず、若干見当違いなことを口にしたようだ。リディアンははぁ、と、深い溜息をついた。
「ちゃうわ。……外みてみぃ外」
「外?」
天幕の奥に逃げ込んだリディアンを放置して、天幕の戸布をそっと上げる。
さっきまで忌々しいほどにぎらぎらと照りつけていた太陽は、厚い雲にすっかり覆われていて、その雲からはしとしとと、水滴が地上に降り注いでいた。
「ああなんだ、雨か」
「なんだ雨か、やないわ……」
はあ、と、またリディアンが溜息をつく。これはまた重症である。
以前から、火のジンである彼が水を苦手としている事は聞いていた。しかしここまで陰鬱な顔になるとは、予想外だった。調子が狂う。
「……なんでオレが出かけてるときにかぎって降ってくるねん……」
「災難だったな」
適当に清潔な布を放ってやると、リディアンはそれでがしがしと頭を拭いた。
「よっぽど嫌なようだな、雨が。力でも吸われるのか?」
「嫌なもんは嫌なんよ。アーリクはんは雨好きなん?」
好きか、といわれると難しい。しかし外を歩きたくない晴天と、陰鬱で冷たい雪に比べれば、曇りの次にましな天候である。
「日が翳るし、砂埃がおさまるから、もう少し頻繁に降ってくれてもいいと思う」
「そんなんかなわんわぁ、勘弁してや」
ちらり、ともう一度戸布を薄く開ける。リディアンには致命的な雨であっても、アーリクにしてみればこの降りは、外套一枚で外出できる程度の小降りだった。
ふと見れば、リディアンが布を放り出して、しきりに髪を手で梳いている。その合間から湯気が上がるのをみて、アーリクは首をかしげた。
「どうした?」
「水、うっとーしぃから乾かしとるんや」
成る程、火の魔法を応用しているらしい。原理はさっぱり分からないが、まあ便利なことである。
「それはまた、便利だな」
リディアンはその作業に忙しいようで、返事は無かった。
風とともに、若干雨脚が強まってくる。どうせすぐ止むだろう。アーリクは持ち上げていた戸布を降ろした。その途端、閉じた布がまたばさりと開かれたものだから、入ってきた人物を凝視してしまった。
「こ、こんにちはっ……!?!?」
入ってきた桃色の髪の少女は、アーリクを見るなり目を白黒とさせ、戸布にしがみついた。ああ、また仏頂面で驚かしてしまったようだ。
「シーリーンか、すまない、驚いただけだ」
むしろ相手の台詞だと思いつつも、少女を天幕に招き入れる。
「こ、こんにちは、アーリク先生。ポ、ポチ先生いらっしゃいますか?」
まだ若干怯えが残っていたが、シーリーンは笑顔で挨拶をしてくれた。
「ポストーチは今出かけている。約束があったのか?」
「あ、はい。本当はもうちょっと早い時間だったんですけど、遅くなっちゃって」
そういえば、出かけていく同僚が、約束のことを口にしていた記憶がある。二人とも、雨で予定が狂ってしまったのだろう。
「いらっしゃらないなら、また来ますね」
「まだ雨が降っているだろう?どうせポストーチも晴れたら戻ってくる、ここで待っていればいい」
それほど長く外にいたのではないだろうが、それでもシーリーンの外套と髪は、些か濡れて色濃くなっていた。
このまままた雨の中を歩かせ風邪でもひかせては、医師の名折れである。
「え、でも」
リディアンは患者ではないのか、というシーリーンの視線に、リディアンがにこっと笑った。
ようやく髪が乾いて、調子が戻ってきたようである。今日はじめて見せる笑顔だった。
「オレも雨宿りやでー」
「そうなんですか?」
「そうそう。ほらおいでぇリーンちゃん、髪乾かしたげるー」
どうしよう、といった顔のシーリーンに、アーリクはとりあえずこれで拭きなさい、と布を手渡した。
「砂漠の通り雨だ、そんなに長くは降らないだろう」
菓子ならいろいろあるしゆっくりしていけと告げれば、シーリーンはにこりと嬉しそうにはにかんだ。
「それじゃあ、お言葉に甘えちゃいます」
「アーリクはん、オレもお菓子欲しいー」
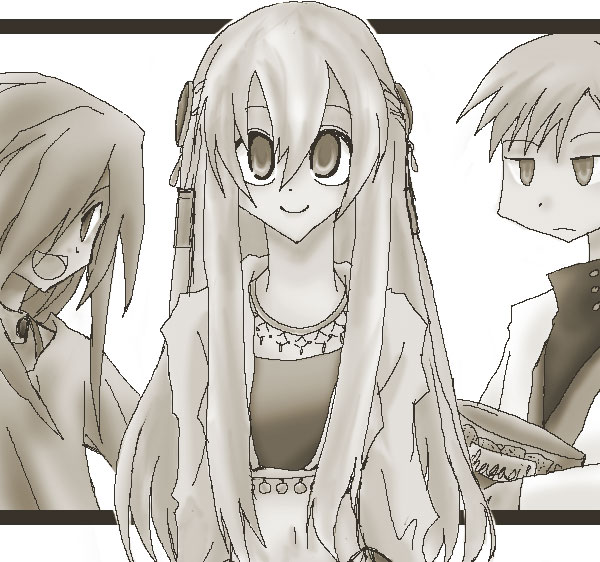
すかさず手を上げたリディアンに、わかってると答える。
「では、茶でも入れよう。リディアン、元気が出てきたのはいいが天幕を燃やすなよ」
準備をしようと、二人に背を向ける。明るい声が背後から聞こえ、微かに口元が綻んだ。
雨であっても晴れであっても、天幕の中は平穏だった。

|