依頼
<終章、呪術師と護衛から詩人へ>「でも残念だったな、最後の譜面。メモをとってる暇も無かったでしょ?」
「うう、覚えてる限りで書き起こしたんですけど」
流石にちょっと自信が……と眉を下げる少女は、がさごそと何枚かの手書きの譜面を取り出した。ソティスとバッサームが受け取って覗き込む。
あの騒動から一夜あけた翌日、礼拝堂への道の途中に設けられた公園の一角に三人は居た。ソティスとバッサームをマリアールが朝の散歩に誘ったのだ(呪術師は例によって天幕から引っ張り出されたらしいのだが、護衛は詳しくは聞かなかった)。日差しは暖かく、散歩には申し分ない。
「あの一回だけで、大したもんだな」
感心するソティスの横で、バッサームも笑って頷く。
「ええ、流石ですね。大体あっていますよ」
え? ときょとんと問い返すマリアールの前で、白い布が揺れた。
ひらひら。
「うわあああ!」
確かめなくても見当がつく。その布きれに浮かぶ紋様は多分、最後の譜面なのだろう。差し上げます、と渡されたマリアールが嬉しそうに礼を言うのに、呪術師は目を細めている。
「何時の間に」
これも何度目かの呆れたソティスの呟きに、乗りかかった船というやつですから、と男は含み笑いで答えた。もういいよそれは、とおざなりに返しながら、ソティスは何かに引っかかったのか首を傾げる。
「ん? ……あなた、楽譜読めたの?」
「まあ一通りは」
しれっと答える男に、ソティスは思い切り脱力した。
「なら、自分で歌えばよかったんじゃ」
「子守唄は母親が歌うものですよ」
ねえ?
悪戯っぽい眼差しがちらりとマリアールに向けられた。たぶんそれは、昨日の別れ際のあの少年――アクラムとの遣り取りを揶揄している。それが判ってマリアールは思わず頬を赤くした。
ありがとう、
そういって昨日の別れ際、アクラムはマリアールたちに頭を下げた。
それから顔をあげ、にこりと笑って言ったのだ。
『あれ、マリアールがうたってくれたあの歌。小さいころ、かあさんが歌ってくれた子守歌だったんだ』
『歌ってるマリアールはちょっと母さんに似てた』
その言葉にマリアールは赤面し、狼狽し、ちょっと血を吐きかけた。
『ごごめんなさい、わたしには心に決めた人が…っ! かはっ!』
『いいんだ、』
言いたい事は、言えるうちに言っておかなくちゃと思っただけだから。そういったアクラムは、手に乗せた小さなイヤリングに凝乎と視線を注いで、それから穏やかな顔でもう一度マリアールを真っ直ぐに見ると。
『だから父さんにこれを届けにいくよ』
イヤリングを握り締めて、笑ったのだ。
そのときに聞いたのだが、彼のお母さんは地のジンだったそうだ。それを聞いて、ああ、あの蜘蛛は地属性のルフだったのかと納得がいったものだ。もしかしたら彼女の友達みたいなものだったのかもしれない。彼女の最期の場所を護っていたのかもしれない。
そしてジンである彼女は最期まで、少女の外見をしていたのだという。
「ご主人から聞いた話だと、詩人だったそうだが」
「少女の姿をした地のジンで、詩人……何だか言い伝えに似てますねっ」
もしかしたら、ご当人だったのかも。二人が交わす会話に、バッサームが冗談めかしてひそりと笑う。ソティスとマリアールはちょっと顔を引き攣らせた。
「まっさかぁ……」
肯定する材料も無いが、しかし否定する材料もないのが微妙だ。胡散臭い呪術師の台詞に何だか落ち着かない気分になりながら、マリアールは昨夜隊商宿に尋ねてきたアクラムの父の事を思い出す。
現れたアクラムの父は、息子とそう変わらない背丈の少女に丁寧に頭を下げた。そして少ないですが御礼です、と小さな袋を差し出したのだ。大きさの割に重さのあるそれに驚いて、そんな、もらえません! とぶんぶん首を振ったマリアールに(因みに貧血を起こしてちょっとよろめいた)、彼は困った顔をして――思いついたようにこういった。
『貴方は息子に歌を聴かせて下さったそうですね。ならこれは詩人としての報酬です、それならいいでしょう?』
それで断りきれなくなり、堂々巡りの議論の結果、その袋の中身を半分にしてもらうことで話は落ち着いた。良かった、と微笑んで暇を告げる男に、マリアールは慌てて声をかけた。
『私たち、まだあと何日かこの町に居るんです』
『あのお店のご飯美味しかったから、このお金でご飯を食べに行きますねっ』
『またおしゃべりしましょうね、良かったら私の歌も聴いてください』
『今度はアクラムさんと、お父さんと、……ええっとみんなで!』
急いで言ったのでつっかえつっかえになったが、ちゃんと伝わったようだ。楽しみにしていますと笑った顔は、とてもアクラムに似ていた。
からり、
マリアールは鞄から飴の瓶をとりだして揺らす。昨日随分と活躍したラッキーアイテムなるキャンディは、つまりは唯ののど飴だ。
幾つかを残すのみとなったその瓶を開けて、ひとつ口に入れた。
父は譜面が読めるが、あのタイルの場所はわからない。子はタイルの場所はわかるが、譜面は読めない。
それでも、彼女は二人の手元にあれを残していった。
見つけて欲しかったのだろう。
夫と子に、自分を。
「わたしたち、知らないうちにアクラムさんのお母さんの依頼まで引き受けていたんですかね」
そうかもね、と護衛は肩を竦めた。
なら尚更正当な報酬でしょう、と呪術師は笑った。
二人に聞いてみると、アクラムの父親は護衛と呪術師のところにも行ったらしい。
「貴方は殆ど何もしなかったんじゃないか?」
「下さるというものは頂いておくものでしょう」
「ちゃっかりしてるなァ」
マリアールは二人の会話を聞きながら、気持ちの良い風に口元を緩める。
ころり。
飴を口の中で転がす。
「そうだ、私もお二人にお礼をしなくっちゃいけません!」
だっていっぱいお手伝いしてもらいましたし、ばっと顔を上げたマリアールが言うと、ソティスは笑った。
「わたしはたくさん歌を聴かせてもらったでしょ? それでいいよ」
「ええ~……。っじゃあ、バッサームさんは?」
「ふふ、……歌ですか。それは良い」
「え?」
「もしお願いできるなら」
もう一度あの歌を。
言われてマリアールが思い切り頷くと、二人はその力の入りようが可笑しかったのか揃って笑う。
「あなたもご一緒に如何ですか? 序でに一杯」
「ふむ、付き合おう。……そうだな、場所はあの店でどうかな?」
ね、マル。
護衛は片目を瞑って、詩人に笑いかける。

少女は手元の譜面を握り締め、嬉しそうに頷いた。
(歌を探していた)(あなたを探していた)
(あの時貴女が歌ってくれた、歌を)
(母の胎内で聴いたような)
(やさしい、うた)
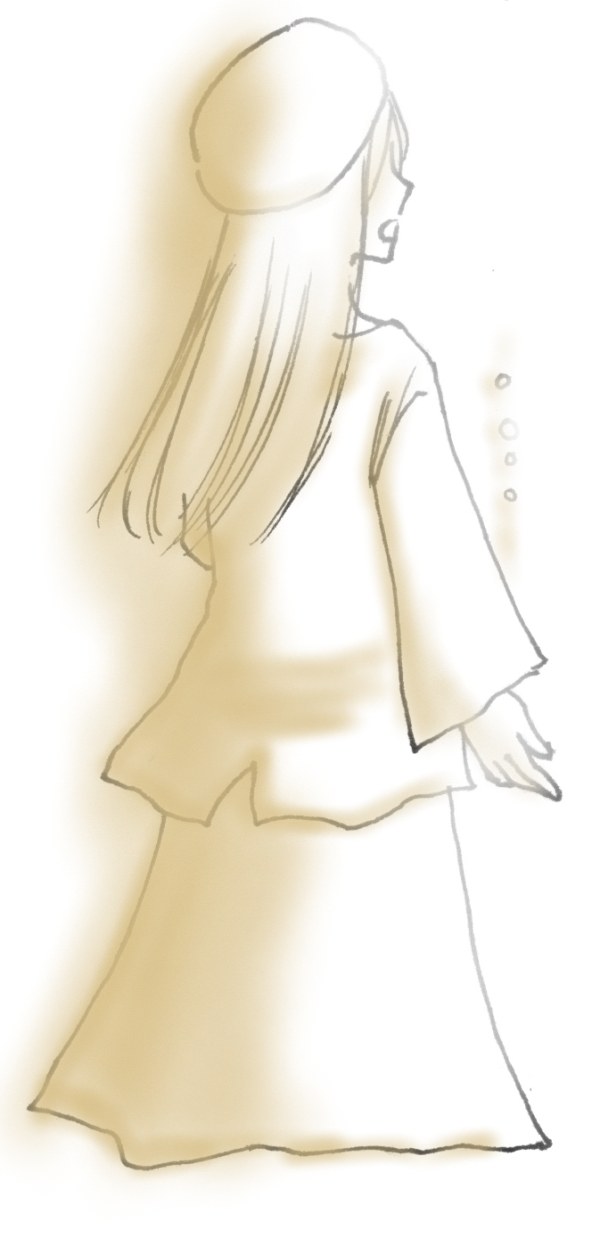
《前のページ》